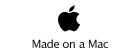ゲノムが運動しているって ?
私たちのグループでは、生物が地球上の環境にあわせてゲノムや遺伝子を多様化させてきた原理に興味を持っています。どうしてゲノムは変化できたのでしょう? どうしてゲノムは新しい遺伝子を作り出せたのでしょう? 一体どういう研究をしたら、この生命の謎が解けるのでしょう?
植物細胞の中にある葉緑体は、大昔は独立生活をする光合成細菌だった、って知ってましたか? そうです、細胞内共生進化、というやつです。植物の葉緑体というと、光合成をはじめとした植物生理学の研究対象と思われがちですが、実は、地球上の生命の謎を解くための重要なヒントが隠されています。「光を食べる生き物たち」がどうやって出現し、進化し、繁栄したのかを、ゲノムの仕掛けからみてやろう、というわけです。 因みに、「光を食べる」と言えば、ウミウシ(貝殻のない貝の仲間)には、海藻から葉緑体だけを取りこんで、ちゃっかり光合成をする連中がいるって、知ってましたか? 今年はめでたくウミウシの研究調査費用が採択されたので、光合成ウミウシ探検隊を(まず近場の海に)派遣するぞ!
閑話休題。
私たちはゲノムの運動原理を探るために、現在、「葉緑体から核への遺伝子移動」と「葉緑体RNAエディティング」という二つの現象に、研究の焦点を合わせています。