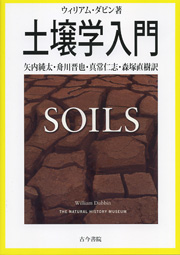「土壌学入門」
ウイリアム・ダビン著
矢内純太・舟川晋也・真常仁志・森塚直樹訳
古今書院、2009年発行、B5判 123頁、定価3600円(税別)
目次
第1章 土壌の生成と組成
第2章 土壌の分類と地理的分布
第3章 土壌生物
第4章 土壌肥沃度
第5章 土壌の利用と誤用
第6章 我々の将来と土壌
訳者あとがき (「土壌学入門」より)
本書は、William Dubbin著 “Soils(土壌)”(The Natural History Museum:英国自然史博物館、2001年)の全訳である。
本書は、農業国であるとともにバラをはじめとするガーデニングやナショナルトラストに代表される環境保全に極めて熱心な国である英国において、一般の人々向けに書かれた本である。すなわち、ひろく世に知られている英国の自然史博物館が、自然科学に興味を持つ多くの人々に土壌のことをよく知ってもらいたいという意図で発行したもので、専門家ではないが土壌に関心がある、という読者にも、非常に分かりやすい内容となっている。
カラー写真や図表が数多く掲載され、土壌の姿や役割がイメージとして捉えやすいことも、本書を分かりやすいものにしている。従来、土壌学に関する教科書や読み物は、正確さを重視するあまり専門性の高い記述が多く、一方で写真などを用いた情報発信をあまり行なってこなかった。そのため、土壌について少し学んでみたい、という初学者にはやや敷居の高いものであった。その意味で、本書は、土壌学を専門に学びたい人々はむろんのこと、大学の教養課程などで土壌を初めて学ぶ学生諸君や、家庭菜園や庭づくりあるいは環境問題への取組みを通じて土壌について知りたくなった人々など、これまで土壌にあまり興味のなかった読者にも、楽しみながら読み進めていってもらえるものと期待している。
土壌は、食料生産の基盤であるとともに生態系の基盤でもあり、空気や水と同様、21世紀の人類が健やかに生きていくために不可欠な地球の「財産」である。しかし、本書にも書かれているように、67億を越える人類は従来以上に土壌に負荷をかけ続けており、土壌を適切に利用しその保全を図ることが一層求められている。一方で、その役割の重要性にも関わらず、人々の土壌に対する認識は、まだ十分深まっているとは言い難いのが現状である。そのため、この本が読者の(あなたの!)土壌に対する興味と理解を深めることに少しでも役立つならば、訳者としてはこれ以上の喜びはない。
翻訳は、1章を舟川、2章を真常、3、4章を矢内、5、6章を森塚が、それぞれ担当した。十分に推敲はしたつもりであるが、誤訳などが見られる可能性はある。これに関しては、読者諸氏のご叱正を期待したい。
最後になったが、本書の出版にあたり、終始熱心にお世話下さった古今書院の関田伸雄氏に心から謝意を表したい。
2009年1月 矢内純太、舟川晋也
真常仁志、森塚直樹
書評 (「圃場と土壌」2009年4月号より)
土壌肥料学という分野は、それを専門とする人間でも体系的に理解するには骨が折れる。特に大学の教科書などは、とっつきよいものではなかった。しかし、この本は、絵本かと思われるほどにビジュアルにやさしく土壌を語ってくれる。これは、原著者が勤務する英国自然史博物館流なのかもしれないが、それでいて、一般の方に土壌肥料学の本質を的確に伝えるだけの質の高い情報が過不足なく盛り込まれている。たとえば、使用されている粘土の電顕写真は、粘土鉱物を化学式で示すよりも直観的に層状構造を感得させてくれるし、世界の主要な土壌タイプの断面写真などは土壌の成り立ちについて大いに想像力を刺激する。
筆者の興味のある土壌肥沃度診断のところには、「不十分な情報に基づいて推理することのいかに危険なことか」-シャーロック・ホームズなどと英国流の洒落が入っていたりするが、そのあとに続く本文では、「植物は養分吸収を向上させるために菌根をはじめとする様々な戦略を取り入れている。これら生物的な戦略を真似て可給態養分を迅速かつ確実に測定できるのが、良い土壌診断である」などと実に適切かつ分かり易く土壌診断というものを紹介し、土壌診断法を確立してきた歴史が要約されている。コラムで紹介された「手ざわりによる土性の判定法」は、操作と判定基準が明確であり熟練せずとも判定できるのではないかと思った。今度野外で試してみたい。
本書の構成は、第1章 土壌の生成と組成、第2章 土壌の分類と地理的分布、第3章 土壌生物、 第4章 土壌肥沃度、第5章 土壌の利用と誤用、第6章 我々の将来と土壌であり、巻末には用語集や参考文献、訳者の追加した参考文献等もある。
本書を訳したのは、4人の気鋭の土壌肥料研究者であり、英国での研究経験のあるメンバーが原著に惚れて広く紹介したいと思ったのが発端に違いない。専門家ならではの訳注や、わかり易い解説図を本文中に挿入するなどの工夫も凝らされている。「土とは何?」と思った方には、ぜひともご一読をお勧めしたいし、大学の教科書のサブ教材として最適ではないかと思った。
鳥山和伸(国際農林水産業研究センター)
![]()