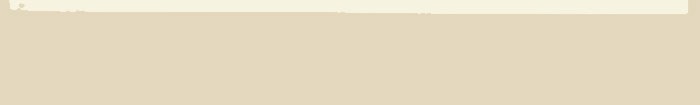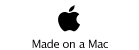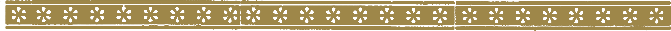2011年5月17-18日の学生実験の結果


以下は、5月18/19日の生物機能コース実験 Ⅰ の各班の結果です。1班から6班までの結果を示してあります。各自、ダウンロードして、レポートに使ってください。
実習レポートの作成


実習レポートは、2011年 6月1日 (水曜)午後5時までに、3号館3218室のレポートボックスに提出してください。質問があれば、メールで尋ねるか( obokata@kpu.ac.jp まで)、研究室を訪ねてみてください。

1. PCR実験でDNA断片の増幅物がバンドとして現れてこない場合、一般に、次のような理由が
考えられる。今回の実験結果を考えるヒントにせよ。
・ 鋳型となるDNAに、プライマーとの相同配列がなかった。
・ 鋳型となるDNAの量が不充分だった。
・ 反応液の成分に問題があった。
=(プライマー、バッファ、酵素、等が本来の働きをしなかった)
・ 反応液のなかに、反応を阻害する物質が持ち込まれた。
・ 反応の温度や時間、サイクル数などの設定が適切でなかった。
2. PCR実験では、理想的には、n回の反応サイクルで、DNA断片は2のn乗倍に増加する。
つまり、20回の反応サイクルで、DNA量は100万倍になる。PCR実験は非常に検出感度が高い.
-
3.PCRではDNAの検出感度が非常に高いため、ほんの微量のサンプルの混入によっても、 バンド
が現れることがある。
-
4.PCR実験では,理論的には複数のDNA断片が増幅される場合でも、一部のDNA断片しか検出されないことがある。(個々のDNA断片の増幅効率は、実際には、断片の長さや塩基配列などの影響を受ける。このため、増えやすいバンドと増えにくいバンドが混じっていると、例えば30サイクルのあとでは、両者の量比には、とんでもない差がついてしまう)。
レポート作成のヒント

ハネモからのDNA抽出について
1. アガロースゲル電気泳動像のうえで、マーカーDNAのEtBr発色量と比較し、ハネモから
抽出したDNAのおおよその回収量を推定する。
2. 抽出した核酸の吸収スペクトル、吸光度と、ゲル電気泳動像を比較すると、何がわかるか?
PCR実験に関する補足説明
ハネモとウミウシのPCR結果の比較について
1. テンプレート(=鋳型DNA)とプライマーの組み合わせの意味をよく考えよ。
2.ポジティブコントロール(ポジティブ対照処理区)、ネガティブコントロール(ネガティブ対
照処理区)の意味をよく考えよ。
3. その他、配布した「実験のテキスト」に記した考察の方法やヒントなどを参考にせよ。